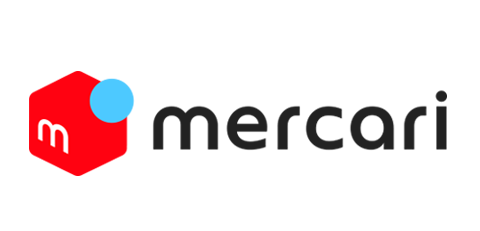1970年代のジャパンヴィンテージギターの中でも、グリーンラベル機のギターはリペア次第で高い演奏性をキープでき、なおかつ赤ラベルの影に隠れて価格が安いため、コストパフォーマンスの高い選択だといえます。
この記事では、グリーンラベル機のヤマハFGシリーズの中でも隠れた名機と呼ばれるYAMAHA FG-170について解説していきます。実物のサウンドサンプルも動画で聴いてみてください。
リペア済みFG-170
YAMAHA FG-170とは?

YAMAHA FG-170は1972年から1974年という短い期間に製造されたヤマハのアコースティックギターで、赤ラベルの直系の後継機ということになります。赤ラベルといえば粗削りながら爆音で、とにかく良く鳴るギターというイメージですが、グリーンラベル機のYAMAHA FG-170も、その性格をまっすぐ継承したようなギターで、やや小ぶりなフォークボディでありながら、非常に良く鳴るギターと言えるでしょう。
やや小ぶりなフォークボディですが、低音はずっしりと響きますし、高音は金属のようにキラッとよく通る音です。また、箱の中でうわんと響いている感じが伝わるので、非常に豊かなサウンドに聞こえます。しかもこもっている感じがなく、すっきりと抜けたサウンドというのもポイントです。
もし、コレクターとしてギターを集めるというのなら、赤ラベルの方が満足感があるかもしれません。しかし、プレイヤーズヴィンテージとして捉えるなら、グリーンラベル機のギターの方がおすすめです。なぜなら赤ラベル機のギターに比べて、楽器としてのパフォーマンスには差がなく、しかも価格はかなり安く売られているからです。
YAMAHA FG-170はトリプルオーサイズ相当のフォークボディなのですが、ここまで良く鳴ってくれるのなら、ドレッドノートでなくても十分ではないかと感じます。また、YAMAHA FG-170は合板のギターということで「安いギターだったんだ」と思われがちです。しかし、当時の定価は1万7000円でした。これは大卒初任給の約1/3に当たる金額です。
今の貨幣価値に換算すると8万円相当のギターということになり、例えば、Headway Japan Tune-upシリーズやOvation Celebrity Eliteなど中級機に匹敵する価格帯ということができるでしょう。そのギターが現在の中古市場で1万円前後から手に入ります。リペア済みのYAMAHA FG-170も2万円から3万円程度で手に入りますから、実際にはかなりお得感のある楽器だといえるでしょう。
YAMAHA FG-170の歴史的背景

現在のヴィンテージギター市場において、YAMAHA FG-170のようなグリーンラベル機のギターはかなり微妙な立ち位置にあります。品質を客観的に判断するとすれば、赤ラベルと同等もしくはさらに改善されているので、赤ラベル以上の品質でありながら市場の価値はかなり低いというアンバランスな傾向があります。
赤ラベル機の特に知名度を牽引しているFG-180の圧倒的な人気の影に隠れてしまっており、下位モデルの評価が低いということができるでしょう。これはコレクター市場でしばしば最初のバージョンやオリジナルバージョンに対して、実際以上にプレミアがつき価値が引き上げられてしまうということに原因があるのかもしれません。
しかし、いいヴィンテージギターを実際に弾いてみたい、弾き込んでみたいという人にとっては、YAMAHA FG-170のようなグリーンラベル機のギターは安くて、しかも音が良く、リペアさえきちんとしてあげれば、非常にいいギターになり得ます。
ヤマハのビンテージの中で、初期のヤマハギターの個性を保ちつつ、価格も安いグリーンラベル期は独特の立ち位置といえるでしょう。
YAMAHA FG-170の構造や素材

YAMAHA FG-170はフォークスタイルのボディ形状を採用していますが、これはアメリカのマーチン社でいうところのオーケストラモデル(OM)やトリプルオー(OOO)に相当するサイズ感です。FG-180やFG-200のようなドレッドノートサイズと比較するとYAMAHA FG-170はかなりコンパクトで、そのおかげで平均的な日本人にとってはむしろ弾きやすいサイズとなっています。
特に長時間練習した時の疲れ具合が少なく、ヴィンテージギターをプレイヤーズヴィンテージと捉えて「がっちり弾き込んでみたい」という人にとってはかなり良い選択といえるでしょう。
ただ、現在の基準から考えると、ネックは太くがっしりとしています。慣れれば問題なく弾けますが、最初に持った時の違和感は感じるかもしれません。
また、木材としてはトップの材にはスプルースの合板が使われています。最近の安い合板のように真ん中に安価な木材の板を挟み、スプルースでサンドイッチした見た目だけスプルースというようなものではなく、スプルースを3層に組み合わせた構造となっています。
このトップのスプルース合板の出来がかなり良いため、非常に良い音が鳴るのではないかと筆者は考えています。また、ボディのサイド&バックはマホガニーの合板で間違いないでしょう。こちらの合板はトップの合板のような単一の木材のみの合板ではなく、現在のギターに使われている合板と同じようなものと考えられます。
ネック材については、マホガニー、また指板とブリッジにはローズウッドが使用されています。これは当時の標準的な仕様ですが、ローズウッドなどは現在ではなかなか良いものが手に入りにくいため、今のギターと比べて決して悪いものを使っているというわけではなく、むしろかなり品質の良いものを使っているのではないかと考えられます。
YAMAHA FG-170の音響特性と演奏適性
YAMAHA FG-170の音を一言で表現するなら温かみがあり、明瞭かつパワフルなサウンド。多くのヤマハFG愛好者が口にする「バカ鳴り」という表現は大げさとも言い切れませんが、若干言い過ぎではないかとも思われます。最近の10万円クラスのギターと十分比較しうるサウンドだということは間違いないと思います。
YAMAHA FG-170の市場価値とコストパフォーマンス

現在ヤフーオークションやメルカリなどの個人間売買の取引プラットフォームで、どれぐらいの価格で売買されているのかを分析すると、なんとか弾ける状態の個体は概ね1万円程度、リペア済みの個体が2万円から3万円程度と推測されます。修理が必要なジャンク品の場合は5000円や7000円といった価格で入手可能です。
この価格は、実際の楽器としての性能から考えると、価格としてはかなり安いということができるでしょう。ただし、リペア済みで、なおかつしっかりとしたリペアマンによるリペアが施された楽器でない限り、弦高が必ず高すぎるため、非常に弾きにくく、特にその理由のほとんどは元起きですから、リペアが非常に難しいため、自分で弦高を調整しようというのはなかなか現実的ではありません。
筆者が確認した範囲では、弦高が4mm程度の個体がかなり多く、弾きやすく調整するとしたら2mm近く弦高を下げなければいけません。そうすると理論上、サドルを4mm近く削るということになりますが、これは実際には不可能な数字です。
元々この時期のギターはサドルがそこまで高く作られていませんので、ブリッジ及びサドルスロットを彫り込む必要があります。
ブリッジとサドルの調整で追いつかない場合は、ネックリセットを行う必要があります。ただし、このクラスのギターでネックリセットを行ってしまうと、予算的には完全にバランスが取れず、ネックリセットまではやりすぎではないかと考えられます。
そのため、できるだけ弦高が低い個体を探し、4mm未満であることを確認した上で、なおかつブリッジを削り、サドルスロットを彫り込むことで、現在のサドルの高さを4mm近く落とせるかどうか、その辺りが購入を決定するための決め手になるかと思います。